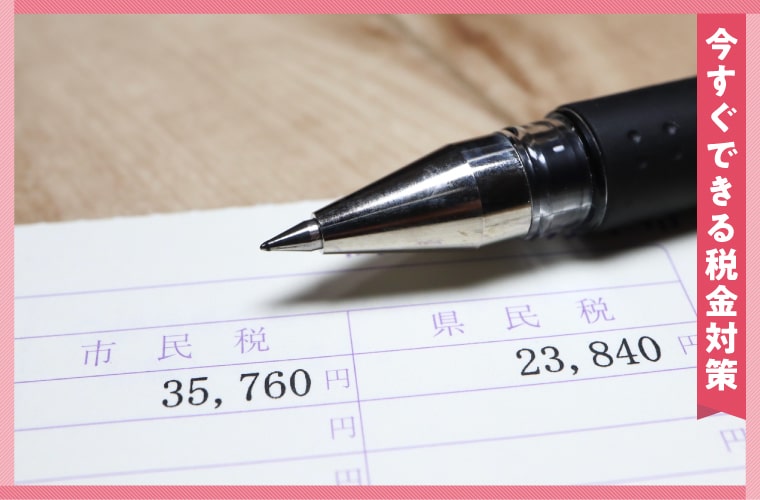
公開日:2023/11/14
会社員などの給与所得者の場合、会社側が申告や納税を行ってくれることが多いため、税金対策について個人であまり考える機会は少ないかもしれません。しかし税金の仕組みや控除の種類について知っておくことで、個人でも節税が可能です。
当記事では、会社員が今すぐできる効果的な税金対策にはどのようなものがあるのか、その方法と知っておきたい控除の種類について解説します。
税金とは、私たちの生活を支えるために国や都道府県、市町村に収めるべきお金のことです。健康で文化的な生活を送れるよう、税金で運営される公的なサービスには、年金や医療保険などの社会保障、水道・道路などのインフラ整備、学校教育などがあります。税金は、社会で暮らしていくために必要なお金です。
会社員や個人事業主に大きく関係のある税金の種類には、「所得税」と「住民税」があります。それぞれについて見ていきましょう。
所得税とは、個人の所得にかかる税金のことです。会社員や個人事業主の1年間のすべての所得から、さまざまな所得控除を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算します。なお、所得税の税率は、5〜45%の7段階に区分されています。
■所得税の税率区分
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
参照
所得税は、所得が多いほど段階的に高い税率となる課税方式である累進税率で区分されています。所得税の納税方法については、会社員の場合は勤務先の会社が本人の給料から所得税を差し引き、本人に代わってまとめて「源泉徴収」という形で納税し、「年末調整」で納税過不足を調整します。個人事業主は、「確定申告」によって本人が前年の所得を申告し、所得税を納付するのが一般的です。
住民税とは、住んでいる都道府県と市町村に納める税金です。住民税には、個人が負担する「個人住民税」と、会社などの法人が負担する「法人住民税」の2種類がありますが、ここでは個人が納税する個人住民税について見ていきましょう。
個人住民税は、住民の前年の所得金額に応じて課される「所得割」と、平等に負担する「均等割」の2つで構成されています。会社員の場合、個人住民税を勤務先の会社が本人の給料から天引きし、個人事業主の場合は普通徴収によって納税します。
税金対策を考えるときによく聞かれるのが「控除」という言葉です。税金の控除は、納税者の事情に合わせて税負担を公平に調整するために設けられています。税金の控除には「所得控除」と「税額控除」があります。
所得控除は、納税者の個人的事情に応じて所得の課税対象となる分を減らし、納税の負担を軽くする制度です。所得控除は、税率をかける前の課税所得から控除を行います。所得控除には下記の種類があります。
<所得控除の種類>
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
詳しい情報については「No.1100 所得控除のあらまし|国税庁 」をご確認ください。
参照
税額控除とは、納税者に特別な事情がある場合に、負担する税金そのものの一部を減らす制度です。計算した税額から直接控除できるため、税金対策には効果が大きいといえます。主な税額控除には下記のようなものがあります。
<税額控除の種類>
配当控除、外国税額控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など詳しい情報については「No.1200 税額控除|国税庁 」をご確認ください。
参照
会社員は、給料から所得税と住民税が毎月差し引かれていますが、税金の仕組みを理解し、控除を活用することで、個人でも節税が可能です。ここでは、個人でできる税金対策に関する制度について紹介します。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、本人と生計をともにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。
医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計から、保険金や公的給付で補填された額と10万円を差し引いて算出します。その年の総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額の5%を引いた金額となり、上限は200万円です。
セルフメディケーション税制は、健康維持・増進や、病気予防を目的として、その年に本人と生計をともにする配偶者やその他の親族のために、1万2,000円を超える対象医薬品を購入し、さらに健康診断などの一定の取組を行っている場合に受けることができる控除制度です。ただし、この控除を受ける場合は、通常の医療費控除を受けることができませんので注意が必要です。
対象医薬品の一覧は、厚生労働省のホームページで確認ができます。
詳しい情報については「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省 」をご確認ください。
参照
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税の控除が受けられる制度です。ただし、自己負担2,000円となる控除額には上限があり、年収や家族構成によって異なります。総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」で控除できる寄附金額の一覧(目安)や、寄附金額控除額の計算シミュレーションができます。
参照
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。加入は任意で、選んだ商品に対して毎月一定の掛金を支払って資産形成ができ、運用の結果、得られたお金は原則60歳以降に受取ることができます。掛金のすべてが「所得控除」の対象となるため、所得税・住民税が節税できるのに加え、運用で得た定期預金利息や投資信託運用益も非課税です。
NISAは、2014年にスタートした個人投資家のための税制優遇制度です。NISA口座(非課税口座)内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税となっています。なお、税制改正において、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されており、非課税保有期間が無期限になります。
生命保険や地震保険に加入している会社員は、1年間に支払った保険料が所得控除の対象です。生命保険料控除は、生命保険の種類によって一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に分けられ、それぞれ控除額の上限があります。地震保険は、年間の保険料の5万円までが控除対象です。
参照
No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられるのが扶養控除です。親族の範囲と控除金額は、下記のようになっています。
<扶養控除額>
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上の控除対象扶養親族) | 38万円 | |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の特定扶養親族) | 63万円 | |
| 老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
参照
住宅ローン控除は、個人が住宅ローンなどを利用してマイホームの新築、取得または増改築をした場合、「住宅ローンの返済期間が10年以上」など一定の要件を満たすときに、所得税が控除される制度です。住宅の種類や入居時期で控除額が異なるため、利用する場合は事前に詳細を確認しておきましょう。
税金の納付にはクレジットカードが便利でおトクです。納付のために外出する必要がなくなるほか、納付金額に応じてポイントを獲得できます。
中でもイオンカードは、入会金や発行手数料が無料で、ほとんどのカードは年会費も無料です。もちろん税金の納付も可能です。
詳しい情報については「公共料金・税金のお支払い | イオンカード 暮らしのマネーサイト」をご確認ください。
さらに、イオンカードでふるさと納税「まいふる」をご利用いただくと、所得税・住民税の控除に加えて、ご利用金額に応じてWAON POINTがいつでも基本の2倍たまるため、よりおトクに活用することができます。
詳しい情報については「はじめるなら【まいふる by AEON CARD】イオンカード決済でWAON POINT常時2倍! 」をご確認ください。
そんなイオンカードのうち、特におすすめのカードをご紹介します。
■イオンカードセレクト

| 年会費 | 無料 |
|---|---|
| 国際ブランド |
|
| 種類・機能 | クレジット/WAON/キャッシュカード |
| たまるポイント | WAON POINT/電子マネーWAONポイント |
| ご利用可能サービス | AEON Pay/Apple Pay/イオンiD/家族カード/ETCカード |
イオンカードセレクトは、イオン銀行のキャッシュカード・クレジットカード・電子マネーWAONの機能や特典が1枚になった、入会金・年会費無料のクレジットカードです。ご利用金額200円(税込)ごとに1WAON POINTがたまるうえ、イオングループの対象店舗なら、お支払い200円(税込)ごとに2WAON POINTと、ポイント還元率が倍にアップします。
これまで紹介してきた制度を利用することで、会社員でも節税することが可能です。納める税金の負担を減らすことで手取り額が増え、そのお金を教育費や老後資金、資産運用などに活用することもできます。
また、クレジットカードで税金の納付を行うことで、ポイントが還元されるのでおトクです。控除の条件や内容をよく理解したうえで、ご自身に合った制度を利用して税金対策を行ってみてはいかがでしょうか。
